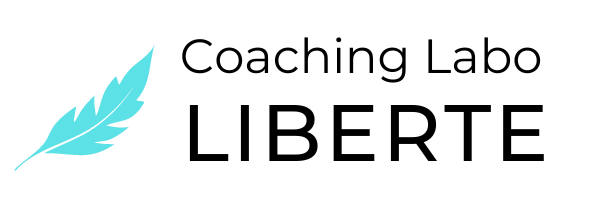「My point of view」は、旅先で出会ったことや日々の生活で気づいたことなど、私の世界の捉え方をエッセイ調で綴ったシリーズです。
「トゥアレグ」
別名で「青の民族」とも呼ばれる、サハラ砂漠をラクダと旅するベルベル系の遊牧民である。
青いターバンと衣装に身を包み、鷹のような鋭いまなざし。彼らにわたしは「ミステリアスで誇り高き砂漠の民」というイメージを持っていた……少なくとも、モロッコを旅するまでは。
メルズーガはサハラ砂漠への旅の起点になる町だ。砂漠の砂と同じ、少し赤味がかった色の土壁で出来た質素な家々の向こうに、どーんと広がる砂丘が見える。中々に壮観。
その砂丘の入り口で待っているのが、大勢のラクダといかにもエキゾチックな民族衣装をまとったラクダ使いのベルベル人たち。サハラの細かい砂を避けるため顔はターバンで覆われていて、鋭い眼だけが見えるのが印象的。

不機嫌そうに鼻を鳴らすラクダの背に揺られ、一時間かけて日没を眺められるポイントに移動。日が暮れたらまたラクダに乗って、砂丘のあいだに作られたキャンプ地に向かう。
ラクダを引く青い衣装の青年たちは、ツアー客の写真を撮る時以外はほとんどしゃべらない。まるで、砂の中に言葉を置いてきたかのように。
キャンプに到着して、モロッコの定番タジンとクスクスの遅い夕食を済ませたあと、自分のテントの裏にあるちょっとしたスペースに座って砂漠を眺める。テントはキャンプの中心にある広場を囲むようにぐるりと立っていて、裏側はプライベート感が満載。
月明かりが周りの岩や草木の影をかすかに映す暗闇の中で、そっと目を閉じる。夏の始めの、少し生ぬるい風が肌に心地よい。広場ではラクダ使いたちが音楽とダンスでツアー客をもてなしていて、後ろから聞こえてくる音があまりにもにぎやかで、思わず苦笑する。
砂漠にはもっと、静寂があるのかと思っていたけれど。

ふと、暗闇の中から誰かが近づいてくる気配を感じた。少し警戒しながら顔を上げると、ラクダ使いの青年の一人だった。
大丈夫か、どこから来たのか、何か必要なら声をかけて、そんな言葉を片言の英語でいくつか交わした後、「スペイン語は話せる?」と聞かれた。話せない、と私が答えると、「そう、じゃあまたね」と言って去っていった。
暗がりに目をこらすと、同じようにツアー客に声をかけているラクダ使いは何人もいるようだ。皆が砂漠の夜を楽しめるように、巡回でもしているのだろうか。
しばし砂漠の静けさを楽しんだあと、マラケシュからの2日間にわたる移動の疲れもあって、早々に自分のテントに引き上げることにした。早々と言っても23時過ぎ、寝るにはいい時間だ。
ところが建付けが悪いのか、扉の鍵が中々閉まらない。それどころか、どうやっても扉が大きく開いてしまう。さすがに全開で寝るわけにもいかないので、思いっきり引っ張ったり角度を変えたりしてみるものの、まるでコントのように扉はいうことを聞いてくれない。
「どうしたの?」
わたしが悪戦苦闘しているのに気づいた別のラクダ使いの青年が、声をかけてきた。鍵がどうしても閉まらない、と説明すると、コツを教えてくれた。昼間と違って青いターバンは頭に巻かれているだけなので、テントの灯りに照らされて、彫りの深い端正な顔立ちと表情が見える。
ありがとう、と笑顔を向けると、「どこから来たの?」とさっきと同じ質問をされる。日本から来たと答えると、「モロッコは初めて?」「モロッコの印象はどう?」「何日ぐらい旅するの?」と流暢な英語で話しかけてきた。昼間とは、ずいぶん印象が違う。

キャンプについてから気づいたのだけれど、ラクダ使いたちの中には英語、スペイン語が得意な人もいて、必ずしもモロッコの公用語であるフランス語が話せるわけではないらしい。
何度か会話のキャッチボールをした後、そのラクダ使いの青年は私の目をじっと見てこう言った。
「僕のらくだに一緒にエサをあげにいかない?」
その瞬間、なぜか、わたしの脳裏にガイドブックの文言がフラッシュバックした。「一人旅の女性は、砂漠で現地男性と二人きりにならないよう注意しましょう」。なるほど。
砂漠の夜、満天の星空、エキゾチックな衣装を身にまといし、優しい異国の若者。20代の頃なら、完全にときめいてしまいそうなシチュエーションだ。ここから砂漠の一夜の恋や、なんなら国際結婚に繋がっていくのかもしれない。
それにしても、サハラ砂漠でラクダと戯れるなんてすっごく面白そう……なんて考えが、のんきに脳内を巡る。

わたしの頭の声は、淡々と続けた。明日は4時起きで、またラクダに乗って朝日を見に行く。そこから10時間バスで移動。今あなたがすべきことは?と。
冷静さが、好奇心を越えていく。
砂漠の魔法はわたしにかかることなく、暗闇の中に溶けていった。
青年のほうに向きなおり、今日はとても疲れているので休みたいと丁重にお断りする。青年は少し残念そうにしていたが、「疲れているならいいんだ、ゆっくり休んで」と言って去っていた。因みに、断った時にも優しい言葉をかけてくれるのは、モロッコの人達の素敵な共通点だ。
扉をそっと占めた後、思わず笑いが込み上げてきた。
日本人女性というだけで興味を持たれて声をかけられることは、海外では少なくない。特に一人旅をしていると余計に。イタリアでもフランスでもいろんなお誘いの台詞は聞いてきたけれども、「僕のらくだにエサあげにいかない?」は中々に斬新だった。
同時に、彼らのことを少し誤解していたかなと反省する。表面的な部分だけで「ミステリアスな砂漠の民」だと思い込んでいたけれど、わたしは本当に彼らを「見ていた」だろうか?
翌朝ツアーグループのメンバーと合流したら、アメリカ人女性がラクダ使いから真剣にプロポーズされたと困ったように話していた。早々に話を切り上げた私と違って、丁寧に対応していた優しい彼女は、「結婚してほしい」と言われたそうだ。国に彼氏がいるといっても、一歩も引かなかったらしい。
かつてはらくだと共に旅をした彼らの生活も温暖化の影響を受け、今ではマラケシュやフェズで絨毯を売る商人になっていたり、海外から押し寄せるツアー客のガイドになっていたりする。サハラ砂漠ツアーで出会うラクダ使いたちも、そんな観光業に携わるトゥアレグの人達の一部だ。

つくづく、「経験する」ことと「知っていること」は違うのだと思い知る。
以前「バーチャルでいくらでもオンライン旅行ができるこの時代に、わざわざ不便な思いをして旅する意味が分からない」と言った知り合いがいたが、実際にこの身で触れることでしか分からないことは多い。
もちろん今で、も遊牧民としての暮らしに誇りを持っているトゥアレグの人達もいるだろう。でもきっと、毎日ツアー客を乗せて行ったり来たりする「この暮らしから抜け出したい」と、切に願う人も少なからず存在するのだ。そんなこと、モロッコに行く前は想像もしなかった。
旅の前に抱いていた「青の民族」へのミステリアスなイメージは音を立てて崩れてしまったけれど、そこにはリアルさが加わったような気がする。本や動画の知識だけでは決して見えなかった、もっと人間くさくて、愛しくなるような世界。
これだから、旅はやめられないのだ。