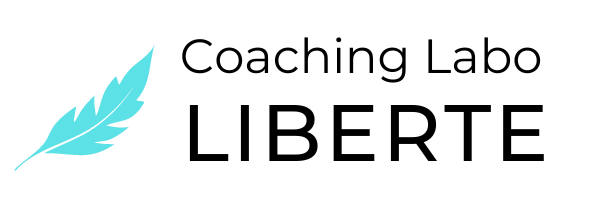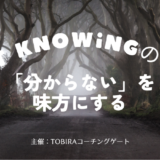「コーチングと禅のあいだ」は、海外生活の経験から日本文化にいっそう興味を持つようになった私が、コーチングの実践と禅の思想を重ね合わせながら探求するシリーズです。
毎回、禅にまつわるキーワードをもとに、コーチの在り方を考えていきます。
今回のテーマは「三学(さんがく)」です。
禅や仏教には多様な解釈があります。この記事では、京都花園大学の講義「禅とこころ」で紹介された表現を中心に、私自身の視点も交えてまとめています。禅の研究者としてではなく、コーチングの学びの一端として書いていますので、そんな視点もあるんだなと、受け取ってもらえたら嬉しいです。
「心をととのえる三つの道」ー三学って何?
「三学」は、仏教の基本的な「修行の三本柱」。
「戒(かい)学」「定(じょう)学」「慧(え)学」の3つから成り立っています。簡単にご紹介すると、
戒(かい)学
自分を律し、心を清らかに保つための約束ごと。「悪いことをしない」「欲に流されない」といった実践を通して、仏教の教えを守り、規則正しい生活を送ることで、悟りへと近づいていく。戒を特に重んじる僧たちは「律僧」と呼ばれる。
定(じょう)学
心を静かにととのえ、物事を「ありのまま」に見る。心を揺らさず、集中を深め、雑念を離れていく修行。禅定(ぜんじょう)と呼ばれる座禅の実践によって、思考を超えた境地へと近づく。定を特に重んじる僧たちは「禅僧」と呼ばれる。
慧(え)学
物事の本質を正しく見抜く力。自分の内側と世界を「ありのままに」観て、そこから湧き上がる直感的な理解を育てる。煩悩を超え、静かな心で世界を見極めることで、悟りへと近づいていく。慧を特に重んじる僧たちは「天台僧」と呼ばれる。
どれか一つだけではなく、これら三つを繰り返し鍛錬することで、「悟り」に近づくと言われています。
さて、この「三学」はそれぞれ、コーチの在り方とどのような関連性があるのでしょうか?
戒 かい─日々を整え、ベストな状態に近づける
たとえお寺でのように規則正しい生活を送っていなくても、「外側―日々の行いを整えることで、内側―心や意識も整っていく」という戒学の考え方は、コーチにとっても欠かせない在り方です。
クライアントの思考のパートナーとして、セッションでベストな自分であるために、日々の暮らしを整えること。睡眠・食事・運動といった基本的な習慣は、私たちの思考の質に大きな影響を与えます。安定した生活のリズムがあることで、クリエイティブな思考や揺るがない自己基盤も育まれていきます。
どのように日々を過ごしているかーそれは、そのままセッションでのコーチの在り方にも表れていくでしょう。
定 じょうー今、ここにあり続ける
ある人が禅師に尋ねた。
「あなたはどのように禅を実践しているのですか?」
禅師は言った。
「お腹が空いたら食べ、疲れたら眠るのです」
「それは誰でもやっていることではありませんか?」
禅師は答えた。
「とんでもない。ほとんどの人は、食べている時には無数の希望を抱き、眠っている時には無数の計画を立てているものなのです」ー禅の物語
「集中を高め、物事をありのままに見る」という定学の考え方は、コーチの在り方において、最も本質的な要素のひとつと言ってもいいでしょう。私たちの思考は本来、とても彷徨いやすいもの。「次は何を質問しよう?」「こうすればいいのに」──そんな声が頭の中に浮かんだ瞬間、私たちは“今ここ”を離れてしまっています。
今ここにいない状態で、どうして「目の前で起きていることを、ありのままに見る」ことができるでしょうか。セッションでクライアントと共にこの瞬間に意識を向け、フィルターをかけることなく物事を見るには、日々のトレーニングが必要です。禅の世界では坐禅が一般的ですが、マインドフルネス瞑想を日々の生活に取り入れているコーチも少なくありません。
大切なのは、気ままに散歩を始めてしまう思考を、そのたびに「今に戻す」という習慣を育むことです。これは、瞑想の時間だけに限りません。信号で立ち止まった時、ご飯を食べている時、誰かと話している時 ── 日々のどんな瞬間にも、私たちは「今ここ」に戻る実践ができるのです。
慧 えー直感で、本質を見極める
「静けさから生まれる直感的な洞察や気づきを、そっと掴む」という慧学の考え方は、クライアントと共にセッションを創り上げるコーチの在り方として、欠かせないものの一つです。多くのクライアントは、自分とは異なる視点を求めてコーチの元を訪れます。
これは決してアドバイスや提案の話ではありません。コーチがクライアントの世界を観察し──見えたこと、聞こえたこと、感じたこと──そこから自然に浮かび上がってくる洞察を伝えることで、クライアント自身が新たな視点を得るきっかけになるのです。
本質的な洞察が生まれるためには、まずコーチが今この瞬間に意識を向け、クライアントの話に五感で耳を傾けることが欠かせません。そして、こうした「今ここ」にある状態を支える土台となるのが、日々の暮らしを整えることです。まさに、三学が伝える在り方そのものですね。
垣根をこえて学ぶ──「雲水」のようなコーチの在り方
それぞれの重んじる学が違う、律僧、禅僧、天台僧。実は互いに交流が無かった訳ではなく、それぞれの立場を守りながら、互いの寺院にもフリーで行き来をしていたそう。修行のために旅を続けた僧たちは「雲水(うんすい)」と呼ばれ、まるで現代のバックパッカーのような自由な生き方をしていたんだとか。
「垣根を超えて、学び続ける」ーこの雲水のような生き方は、コーチにとっても、とても意味があるように感じます。
コーチングは、学ぶことそのものが人生に大きな影響を与えることが多く、その体験ができたスクールのスタイル=尊い!となってしまうこともあります。「コーチングとはこうだ」という視点が確立されるとき、私たちは何に目を向け、何を見落とすようになるのでしょうか。
居心地の良い学び場を離れて、他のコミュニティやグループで学んでみること。コーチングの枠さえも超えて、心理学や禅、リーダーシップ、創造性など、様々な「人」に関わる学びに触れること。
その中で感じる違和感や共感が、コーチとしての成長をまた一歩、後押ししてくれるような気がするのです。

大原亜希
ICF認定PCCコーチ
強みや価値観をヒントに、ビジネスパーソンやクリエイターの「自分らしく働く&生きる」をサポート。大人の自由研究のように、正解のない問いを一緒に探求する対話をしています。

 コーチはなぜ「感情」を扱うのか?
コーチはなぜ「感情」を扱うのか?
 コーチングと禅のあいだ |vol.2「色即是空」ーすべて、変わりゆく
コーチングと禅のあいだ |vol.2「色即是空」ーすべて、変わりゆく