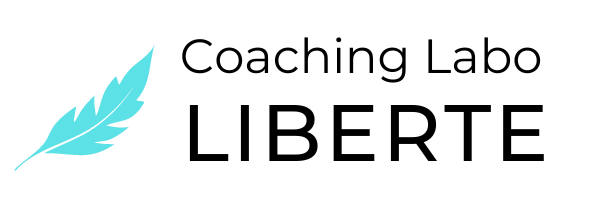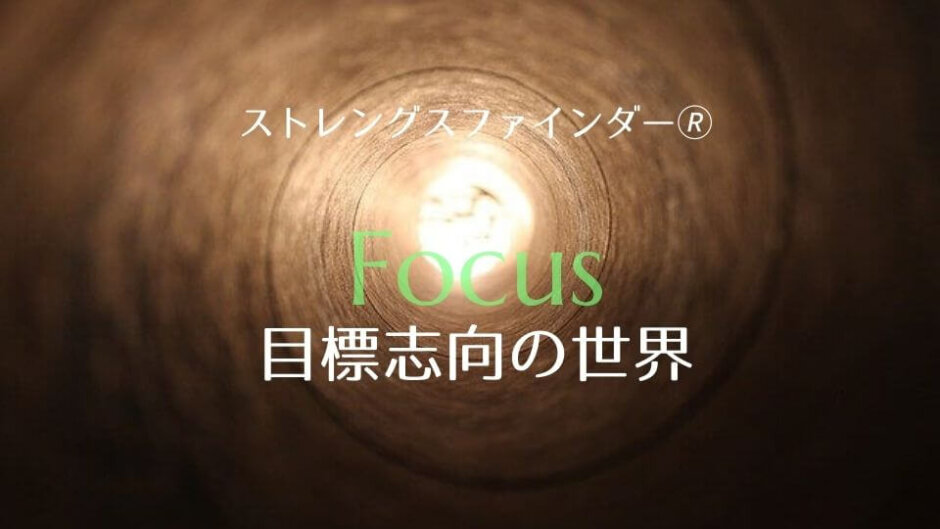この記事ではストレングスファインダーの34資質のひとつ、「目標志向(Focus)」の持つ世界観やその活かし方について書いています。
目標志向はロックオンする
「ロックオン」とは銃やクロスボウなどで、照準の中に目標を捉えることを言います。ひとたび明確なゴールが決まると、目標志向はまるで矢が的に向かって真っすぐ飛んでいくかのように、一心不乱に進みます。「進む」という表現よりもむしろ、頭の中でクリアに描かれた目的地までの道のりを「たどる(Track)」感覚の方が、近いのかもしれません。
会議でも、プロジェクトでも、物事が脇道に逸れると直ちに「軌道修正」を行い、ゴールへ向かうための最短ルートを進み続けます。目的地を自動追尾する機能でもついているのかしら、と不思議に思ってしまうほどです。
「目標があるかどうか」は目標志向にとってとても大切なことなのですが、それ以上に「なぜそれをやるのか」という意味・目的がはっきりしていることが重要です。言葉を変えると、「どこに行くのか分からない、目的地無き何かをやること」には、まるで興味が湧きません。
スタートを切る時には、頭の中に既に明確なゴールイメージがある目標志向。自分のことであれ、チームのことであれ、目標志向にとって目的地とは「辿りつけたらいいな」レベルのものではなく、「確実に辿りつく」場所なのです。クリアな目標を設定すること、またそこへ向かって着実に進み続けているという感覚から、溢れるようなエネルギーを得られる、とてもユニークな才能です。
目標志向は優先順位をつける
目標志向の物事の進め方は基本的には「シングルタスク」であり、一度にひとつのタスクに全集中することで、着実にゴールへと向かいます。弓矢で的を狙うことを考えてみてほしいのですが、同時にいくつもの的に照準を合わせておくのは、中々難しいですよね。
目標志向の頭の中には常に、「これをやることで、ゴールに近づけるのか?」という問いが浮かんでいます。
その都度タスクを決めるよりも、目標が決まった時点で計画をたて、ゴールまでのマイルストーンを設定することも多いようです。目標志向は「Mesurable=測定できる」状態を好む傾向がありますが、それは数値化/データ化によって、着実に自分が前に進んでいるということを実感できるからなのでしょう。
優先順位を決める際、ゴールに到達する上で邪魔になると判断したものは、それが何であれバッサリと切り捨てる一面も持ち合わせています。人が目標に向かって進むとき、人間関係や環境など様々な障害に翻弄され迷うことがありますが、それらは目標志向にとって「ゴールに辿りつけない理由」にはなり得ないようです。
目標志向はフローに入る
心理的エネルギーを一つの方向に向けて集中できている状態は、「フロー状態(Flow)」と呼ばれます。スポーツなどでは「ゾーンに入る」という表現もあるこの超集中状態は、目標志向を語る上では欠かせません。
この理論を提唱した心理学者チクセントミハイによれば、フロー状態に入るには以下の7つの条件があると言われています。
1 自分のやっていることに完全に没頭し、集中している
2 熱中して我を忘れている(日頃の現実から離れているような感覚)
3 内的な明確さの向上(何をするべきか、どれだけできているか分かる)
4 実行可能だと知っている(自分のスキルがタスクに適している)
5 穏やかな感覚(自我を越えて成長していけるような感覚で、自分のことで悩んでいない)
6 時間の感覚が無くなる(現在に徹底的に集中し、数時間が数分で過ぎていくような感覚)
7 内発的動機(フロー状態を生み出す活動そのものが価値になる)
ーチクセントミハイ「Flow the secret to happiness~TED~」
ストレングスファインダーの開発段階で、「フロー状態」は誰もが持つ才能を知る鍵として、研究されました。もちろん目標志向が上位に無ければフローに入れないという訳ではなく、34のどの資質をとっても、この状態になり得ます。
ただ、フロー状態に関して目標志向特有の強みがあるとすれば、「Focus(集中する)」という英語名が示す通り、この才能の持つ傾向性の多くが、フロー状態になるための条件と重なっていることでしょう。
人は誰でもフロー状態になれますが、音や光などの外部要因や自分自身の思考などによって、一度気が散ってしまうと中々元には戻れません。目標志向は一旦集中状態になると、ゴールに辿りつくために必要な事以外はシャットダウンすることに長けています。周りで大きな音が鳴ろうが、携帯のメール通知が光ろうが、お構いなしに集中を長時間保っていられるのです。
それはまるで真っ暗なトンネルの中でゴールという光に照準を合わせ、黙々と突き進むかのようです。時間の感覚、自分という存在の認識すら、どこかへ行ってしまい、ただただ目の前のことに没頭することで圧倒的な生産性を見せます。
目標志向をコントロールする
「フロー」に入っている時の目標志向は、狭いトンネルの先にあるゴールがくっきりと見えるかわりに、トンネルの外で起きていることが、まるで見えなくなってしまうことがあります。それによって、トンネルの外で助けを必要としている人の存在に気づかなかったり、誰かと協力しあう機会を逃したり、もしくは目的地にもっと早く辿りつける新たな選択肢を見逃してしまうことがあるかもしれません。
残念ながら、トンネルの内にいながら外のことに敏感になるのは中々に難しいものです。ですから、「トンネルの内と外の世界を繋いでくれるサポート役」を見つけることが助けになるでしょう。そうすれば、トンネルの外の人に安心してもらいつつ、目標志向もトンネルの中を躊躇なく爆走できるからです。
また目的地に早く辿りつきたい目標志向にとって、外部要因による回り道はイライラさせられるものかもしれません。他愛のない会話や、今この瞬間をただ満喫することは、一見無意味に思えるかもしれませんが、人生には回り道をすることでしか手に入らないものも多く存在します。
「早くいきたいなら一人で、遠くまで行きたいなら皆で行け」
というアフリカの諺があります。周りの人々との繫がりを築いたり、時には回り道することの価値を知り、その選択によってどんな可能性が生まれるのか、時々意識してみましょう。
目標志向でガイドする
ストレングスファインダーの34どの資質をとっても、真に才能が強みとして活かされている時は、主語が「I(わたし)」から「We(わたしたち)」に変わります。
目標志向にとって明確な目標を定め、マイルストーンを置き、着実に前に進んでいくことは、至極当たり前のことだと思いますが、多くの人にとってそれは容易なことではありません。その生来の才能を他者やチームに向けて「目標を明確化すること」や、「目標に対しての行動の優先順位をつけること」を是非サポートしてあげてください。
私たちは仮にそれが目標という言葉ではなかったとしても、「夢」や「やりたいこと」や「実現したいこと」が、少なからずあるものです。ただ「いつまでに?」「どうやって?」といった具体的なプランをたてることが出来ずに、その方向へと中々進みだせずにいたりします。
目標志向の才能が、周りの人が目的地に辿りつくための「ガイド役」として発揮される時、その価値は計り知れません。いつか行きたい場所が、必ず辿りつく目的地に変わり、そこに向かって真っすぐに伸びる道が見えるような瞬間です。
「私たちは目的地へと着実に向かっているのだ」という感覚は、多くの人に前へと進み続ける勇気と、そこへ到達する粘り強さを湧き上がらせることになるだろうと思います。
目的地へと真っすぐに伸びるメインロードを進み続け、確実にそこへ辿りつく目標志向。
わたしが愛してやまない世界の一つです。

大原亜希
ICF認定PCCコーチ
強みや価値観をヒントに、ビジネスパーソンやクリエイターの「自分らしく働く&生きる」をサポート。大人の自由研究のように、正解のない問いを一緒に探求する対話をしています。

 ストレングスファインダー「達成欲」の世界
ストレングスファインダー「達成欲」の世界 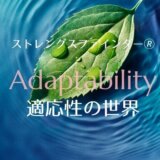 ストレングスファインダー「適応性」の世界
ストレングスファインダー「適応性」の世界