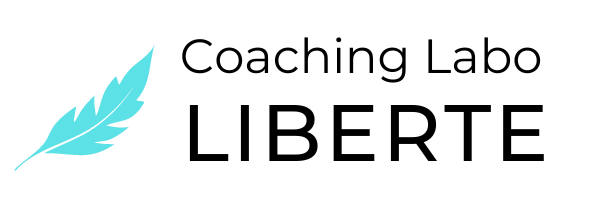お会いした方からよく「世界観がありますよね」とか「ウェブサイトのデザインがすごく好きで」なんて言葉をいただくことがあります。同時に、
「どうやったら、そんなアイディアが出てくるの?」
「クリエイティブになるにはどうしたらいいですか?」
と質問されることも。
今のわたしを創り上げた要素の一つとして、16年の職人としての経験が間違いなく影響してるとは思うんですけれど。
う~ん、なんかアイディアって降りてくる。いや実際降りてくるんです、ホント(笑)。パティシエ時代なら、デザートの色や質感のイメージとか流れ。今だったらワークショップの空間のイメージや、ウェブサイトのデザインなどですね。
で、自分だけではなくて、周りにいる「クリエイティブな人」の共通点って何だろう?って考えてみた時に、「創造力がある=感性が豊か」なのかなと思うのです。
創造力って結局、点と点を繋げることなんです。この世に存在する何かしらと何かしらをくっ付けて、別の新しいものを生み出す力のこと。感性が豊かな人は、この繋げる力がある気がします。日々色んな事を感じているから、繋げる点の引き出しが多い。
感性は生まれつきのものだという人もいますが、私は磨けるものだと思っています。そして磨けば磨くほど、「自分らしさ」も磨かれていくのではないかと。
「やっぱり美術館とかにいくんですか?」
美術館とか、美しいものを見るのは感性を磨くのに良いと言いますが、これは半分正解で、半分不正解だと思います。
実は私、あんまり美術館の絵画や彫刻なんかに興味がありません。好きなのは、「映像」を使った展示やプロジェクションマッピング。大阪の万博記念公園にある、アートと水族館と動物園が合体したミュージアム「NIFREL」なんか、めっちゃ好きです。年パス持ってます。
美術館にも時々行ってはみるのですが、ほぼ立ち止まることなくスルーっと通り抜けてしまうこともしばしば。。。。色々触れてみて分かった、私が好きなものの共通点は「動きがあること」なんですね。
絵画や彫刻は私にとっては止まっているので、あまり魅かれません。でもニフレルに行くと、カクレクマノミが泳いでいる円形の水槽の光が、マゼンタ、コバルトブルー、ダークグリーンと、どんどん色を変えていくので、表情の多様さに思わず立ち止まってしまうのです。
「その一瞬しか見ることが出来ない」アートって、すごく興味を惹かれます。
料理のデザインで言うなら、シンメトリー(左右対称)よりも、アシンメトリー(左右非対称)が圧倒的に好きです。右と左のデザインが違う場合は、大体お皿の中に何も無い空間があって、そこに「動き」が生まれるからです。
アートでも料理でも、美的感覚を養ってくれるものに触れるのは、自分が何に魅かれて、何に魅かれないかを知る機会だと思っています。ただ美しいものに触れるだけではなくて、そこで「あなたが何を感じるか」が鍵なのです。
感性には2種類ある
美しいものに触れたときの感性には、「インプット」と「アウトプット」の二つの方向性があります。
まず一つ目は、アートでも自然でもお料理でも、対象そのものに宿る、思いやストーリーなどを「感じ取ること」。これは「インプット」です。
例えばよくワークショップで使わせていただく場所に、国の重要文化財で三井銀行の大本を作った旧三井家の所有する建物があります。この場所で当時人々がどんな思いでこの庭を見つめていたのだろう、と思いを馳せる。今運営されている方達が、どんな思いでこの建物を守っていこうとしているのかを感じる。
それに対して「自分がどう感じているかを見つめること」。これが二つ目の「アウトプット」。
例えばこの重要文化財は大正時代のもので、大正ガラスが使われています。当時はガラスを真っ直ぐに作る技術が無かったので、歪みがあるのですが、今はその揺らぎがむしろ風流に見えて素敵なんです。時を経たものの中に美しさを見出すこと=侘び寂びを大切にしているから、私はこういう場所に惹かれるのかもしれません。
感性を磨くとは、どちらかというと二つ目のアウトプットの感性なのかなと私は思っています。
自分のなかの
「これが好き」
「これは綺麗」
「これに惹かれる」
「これはテンションがあがる」
みたいな感覚を大切に扱うことです。
そしてそこで終わらずに、なぜ自分はそう思うのか、好きな物の共通点を見つけてみる。そうすると自分が大切にしていること=「価値感」が浮き上がって見えてきたりします。
視覚を閉じて、感性を開く
感性を磨くもう一つの方法は、「五感を意識すること」だと思っています。特に普段多くの情報を取り入れている視覚以外の聴く、味わう、嗅ぐ、触れる、の四つの感覚を研ぎ澄ませることです。
例えば目を閉じてごはんを食べると、味覚がとても繊細になります。普段は気づかない素材の香りにも、気づくと思います。「ダイン・イン・ザ・ダーク」という、真っ暗闇のなかで食事するレストランがあるのですが、ここは正に視覚を外して味わう体験をするための、究極の場所ではないでしょうか。
音楽を聴くときにも、映画を見るのと、映画のCDアルバムを聴くのでは、音の聞こえ方が変わります。
嗅覚を研いでくれるのは、例えば「聞香」。京都のいくつかのお香屋さんで体験できる、利き酒ならぬ、「利きお香」なのですが、順番に回ってくるお香の香りを覚えて出題されるお香を当てます。これもまた、視覚を閉じて香りを聞くと(素敵な表現ですよね)、嗅覚はいつもよりずっと繊細に働いてくれます。
五感は感性と密接に繋がっています。私たちは「美味しいかどうか」を考えません。食べた瞬間に「あ、これは美味しい」と感じますよね。五感を普段から意識して研いでおくと、何かに出会った時に創造力が開きやすくなります。
感性を磨くことから、「自分らしさ」へ
結局のところ、日々の生活の中で「自分の感じたことを丁寧に見つめる」に尽きるのかなあと思います。意識し続ければ、「自分に響くもの」や「違和感」をキャッチするセンサーも鋭敏になります。
そのプロセスの中で自分の価値観が明確になればなるほど、いざ自分が何かを表現しようとするときにも、よりしっくりくるものを選んでいけて。それがやがて、「自分らしい表現」「自分の世界観」へと繋がっていくのではないかと。
感性は、水のように流動的で、変化していくものだと思っています。いくつになっても、世界から何かを感じ続けられる自分でいたいですね。

大原亜希
ICF認定PCCコーチ
強みや価値観をヒントに、ビジネスパーソンやクリエイターの「自分らしく働く&生きる」をサポート。大人の自由研究のように、正解のない問いを一緒に探求する対話をしています。

 「自分らしさ」とは何か
「自分らしさ」とは何か  感性と黄金比
感性と黄金比